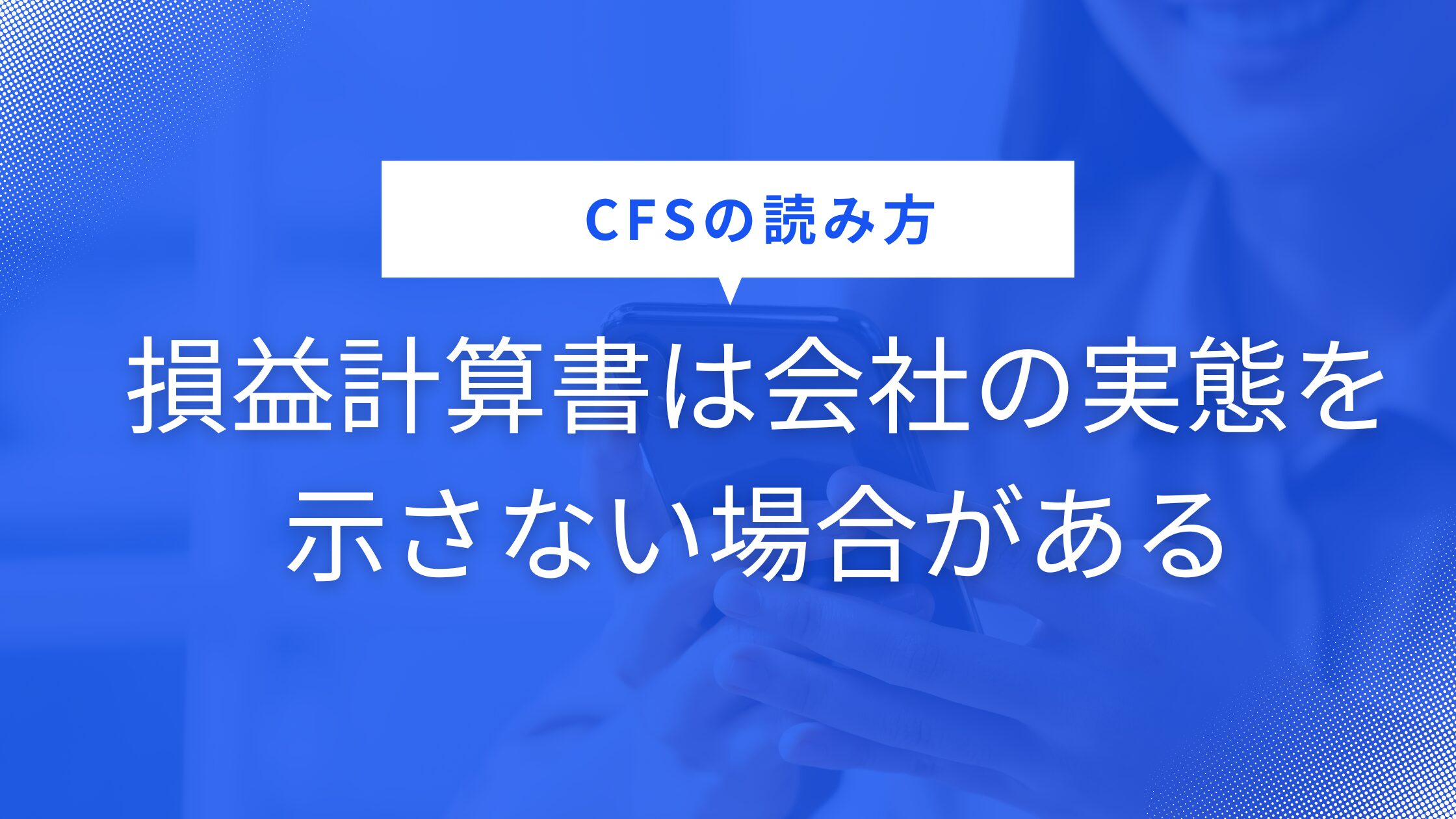損益計算書の目的な適正な期間損益計算
現行の企業会計において損益計算書は、適正な期間損益計算を行い、正確な収益力を表示することを目的としています。したがって収益は販売の時点で、売上原価は売上高との対応により計上されます。
このように発生主義により損益計算を行うことにより適正な期間損益計算が可能となり、損益計算書において正確な収益力を表示することが可能となります。
損益計算書は会社の実態を示さない場合がある
損益計算書における損益計算の仕組みはとても合理的でよく考えられており、素晴らしいと思います。しかし、この損益計算の仕組みには盲点があります。それが過剰在庫です。
キャッシュフロー計算書では商品を購入した金額だけ営業活動によるキャッシュフローのマイナスとなりますが損益計算書では購入した商品が販売されて売上が計上されない限り費用として計上されません。
つまり当期売れ残った商品は損益計算上考慮されることなく、翌期以降の事業年度で販売されるまでは貸借対照表に資産として記載され続けます。適正な在庫金額であれば何ら問題ありませんが過剰に在庫が膨れ上がっている場合には要注意です。
過剰に抱えた在庫金額だけ資金が滞留していることを意味するからです。
その弊害が黒字倒産です。
このあたりの詳細につきましては、前川修満著『決算書はここだけ読め!』が詳しいので興味のある方は読んで見ることをおすすめ致します。