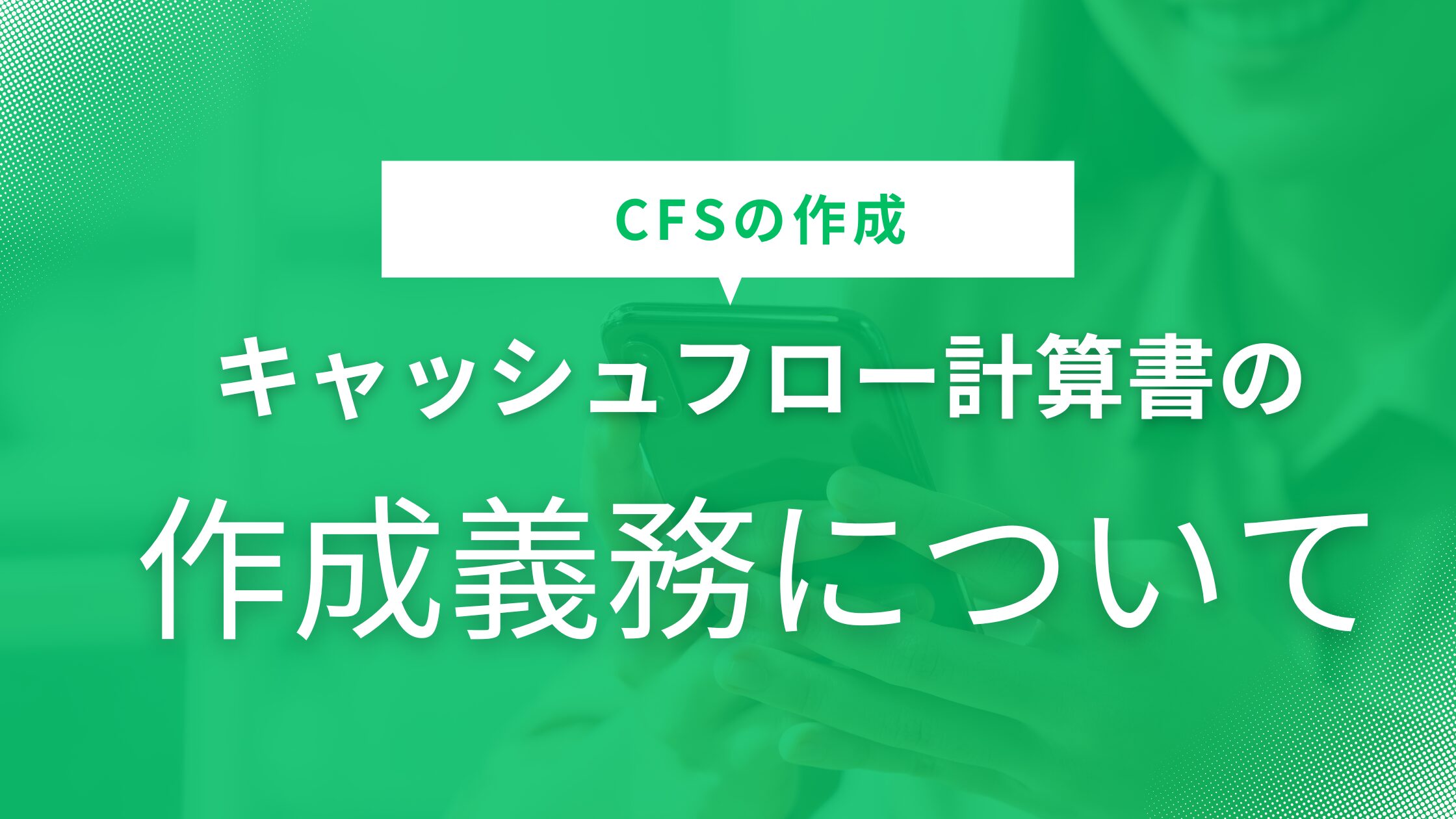キャッシュフロー計算書の作成が強制されている会社
キャッシュフロー計算書は金融商品取引法の適用を受ける上場会社等においてその作成・開示が義務付けられています。具体的なその範囲としては、株式公開会社と非上場会社で会計監査人を設置している会社です。これらの会社はキャッシュフロー計算書の作成・公開が強制的に義務付けられています。
これは税効果会計の適用が強制されれている会社の範囲と同じです。
中小企業はキャッシュフロー計算書の作成義務なし
それに対して、金融商品取引法の適用を受けない中小企業においてキャッシュフロー計算書の作成は任意です。
キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられるのは金融商品取引法の適用がある株式公開会社と非上場会社で会計監査人を設置している会社のみだからです。
キャッシュフロー計算書とディスクロージャー制度
このあたりもう少し詳しく解説しますと、財務諸表(貸借対照表、損益計算書などの財務報告書)は会社法や金融商品取引法といったディスクロージャー制度に基づいてその作成や開示が義務付けられているのですが、我が国においては、株式会社などの営利企業に対して会社法、金融商品取引法、証券取引所という三つのディスクロージャー制度が存在しています。
そのうち、会社法に関しては全ての会社に適用がありますが、金融商品取引法と証券取引所のディスクロージャー規制の適用があるのは株式公開会社と非上場会社で会計監査人を設置している会社のみです。
- 会社法:全ての会社に適用
- 金融証券取引法:株式公開会社と非上場会社で会計監査人を設置している会社
- 証券取引所:株式公開会社と非上場会社で会計監査人を設置している会社
このうち、キャッシュフロー計算書の作成が義務付けられるのは金融商品取引法と証券取引所のディスクロージャー規制の適用がある株式公開会社と非上場会社で会計監査人を設置している会社のみです。
すなわち、株式公開していないような中小企業においてはキャッシュフロー計算書の作成は任意ということになります。
中小企業会計指針においても作成は任意
そして、税理士会などが中小企業者向けに公開している中小企業会計指針においてもキャッシュフロー計算書の作成は任意とされています。ちなみに、税効果会計のほうは中小企業であっても適用すべきとなっています。
中小企業においてキャッシュフロー計算書の作成はあまり必要とされない
中小企業においてキャッシュフロー計算書の作成があまり必要とされない理由としてはいろいろあろうかと思います。
キャッシュフロー計算書は投資家が投資対象会社の選定を行うなどの外部分析において重視されるものではありますがやはり会社にとって重要なのはキャッシュフローではなく利益であること、キャッシュフロー計算書を中小企業が作成したとしても有効に活用できる人材がいない、中小企業の社長の頭の中には感覚としてキャッシュフロー計算書が見えている等。
損益計算書の当期純利益からスタート
キャッシュフロー計算書は損益計算書の税引前当期純利益からスタートして当会計期間における資金の純増加額を経て、当期末における資金残高にたどりつく仕組みになっています。
つまり、損益計算書に計上されている利益と最終的に手元に残った現金に至った原因を明らかにするという働きがあります。このためだけであっても中小企業でわざわざキャッシュフロー計算書を作成する価値があります。